| 632 |
- |
博多駅 |
熊本行き普通列車の最後尾車両にて集合、列車発車。 |
| 705 |
0.0Km |
原田駅 |
到着。駅前広場にてストレッチ。 |
|
|
|
 |
| 730 |
0.0Km |
|
原田駅出発。 |
|
|
|
駅前から九州自動車道とクロスするところまで、市街地の道路を歩く。休日にもかかわらず意外と交通量が多い。高速道路をまたぎ、林道に入る。しばらく林道を歩き、登山口に到着。 |
| 750 |
2.4Km |
|
登山口10分休憩。朝日が気持ちいい。すこし汗ばんできた。 |
|
|
|
 |
|
|
|
山中に入ると、まもなく祠のようなところに出た。念仏の声が聞こえるので何たることかと思えば、祠の上の滝で褌一丁になり禊をしているオッサンが居た。 |
| 831 |
4.2Km |
基山山頂
(404m) |
急に開けたところに出たと思えば、城跡になっている。基山山頂だった。左手に筑紫野の景色が良く見える。また右手にはこれから行く九千部山が。休憩。 |
|
|
|
 |
|
|
|
ここからしばらく稜線の林道歩きとなる。舗装路は登山靴にとってダメージが大きい。4キロ程度だったが、なかなか応えた。また、ここから九州自然歩道の指定路になっており、「
←基山 x.xKm y.yKm脊振山 →」という指導票が 500mごとにあらわれる。指導票の数字から、まだまだ脊振までの道のりが遠いことを実感させられる。
|
| 942 |
8.1Km |
登山道入口 |
小休止。 |
| 1004 |
9.9Km |
|
柿ノ原峠登山道をうねうね歩いて、県道との交差する柿ノ原峠に出た。まだ歩けるので休憩無しでスルー。近くの障害者施設の人が登山道入口でトレーニングをしていた。
|
| 1057 |
12.0Km |
大峠
(545m) |
登り中心の山道をしばらく歩いて、県道と交差する大峠着。小休止。この時点で体力はまだ消耗ゼロ。 |
|
|
|
 |
|
|
|
目指す九千部山まではひたすら登りとなる。標高 600mを越したあたりから、今までの里山風情と打って変わって主尾根らしい道となる。山頂まで1
Kmを残したあたりで左手から車道が近づく。そしていったん山頂とほとんど変わらない高さのピークまで達するも、そこから山頂までの間に1つ鞍部があり、
80mも階段で下らされて、最後に 100mあがって山頂に到達。この鞍部には相当心が折られた。
|
| 1151 |
14.2Km |
九千部山頂
(847.5m) |
山頂では子ども会のような一行が陣取って、にぎやかな昼食タイムにしていた。他にも登山客は多く、展望台のある山頂は満員状態だった。ここで少し長めの休憩。靴紐を解き、足を休める。 |
|
|
|
 |
|
|
|
山頂を出発すると、テレビ送信塔が乱立するエリアを越えて、再び登山道へと入る。テレビ送信塔は
NHK、 TNC、RKB、KBC、FBS…ロゴが並んでいるのだが、何故か TVQだけなかった。
|
| 1249 |
16.1Km |
|
←基山 x.xKm y.yKm脊振山→の指導票の距離が、脊振寄りになる。 |
|
|
|
 |
| 1300 |
16.8Km |
三国境峠
(780m) |
名前の指すとおり、筑前、肥前、筑後の三領地境の峠を通過する。長い長い下りが続く。登りだったらさぞ大変だろう。少しバテ気味のすれ違った人に、「九千部はまだですか?」と聞かれて、お気の毒にと思いながら「まだまだです」と答える。 |
| 1336 |
19.1Km |
七曲峠
(495m) |
九千部以来だらだらと下っていた稜線だが、この峠の手前でストンと落ち込んで、七曲峠へと出た。峠は登山客による駐車で満車状態。峠から那珂川町側へ下りる道路は通行止めになっていた。道路を乗り越えて坂本峠への登山道へ。
|
|
|
|
 |
| 1359 |
20.3Km |
坂本峠
(545m) |
林地測量のテープが邪魔な登山道を進んで、わずか20分少々で坂本峠へ。国道をしばらく歩いて、蛤登山口へ。休憩。少し足が熱を持ってきた。 |
|
|
|
 |
|
|
|
だんだんと植生が脊振らしさを出してきた登山道を登る。この頃になってくると、メンバーもみな無口なってくる。 |
| 1506 |
24.0Km |
蛤水道
(780m) |
林道とクロスする永山峠を抜けると、史跡蛤水道に出る。蛤水道は、江戸時代に脊振山から那珂川を通って福岡に流れていた川を、佐賀側の田手川に疎水する目的で作った水路。ここで小休止。水路の水が非常においしい。また、冷たい水で顔を洗うとリフレッシュできた。
|
|
|
|
 |
| 1546 |
24.6Km |
蛤岳
(869m) |
蛤水道の水で充電して、一気に急登を登りつめて蛤山頂を通過。脊振山頂まで、
1回の小休止を挟むもののほぼノンストップで攻める。しかし既に足にガタが来ており、無言で脂汗を流しながら樹林を歩く。山頂まで
1.7Kmを切ったあたりから、指導票のキロポストがおかしくなり、あと 1.0Kmが出たと思えば、
5〜600m歩いた先に立っていたキロポストも、あと 1.0Km。自衛隊施設を迂回するためだろうか、距離がおかしくなっている。しかも山頂を目の前にして
70mも下る鞍部が出てくるので、気分的にも最悪になった。結局、あと 1.7Kmの地点から3Km以上歩いた感覚だ。最後は木道をわたって、山頂。 |
|
|
|
 |
| 1714 |
29.1Km |
脊振山
(1050m) |
心が半分折られながら、ひとまず脊振山頂直下の駐車場着。自動販売機でリフレッシュしながら、しばし休憩。この自動販売機が曲者で、コーラーを買った人はつまって出てこなかった。その後、山頂まで往復し、痛む足をストレッチでごまかして、出発。ここでテンションは最悪に。椎原峠から下山したい気分であった。
|
|
|
|
 |
|
|
|
日が暮れた。ヘッドランプを装用。 |
|
|
|
 |
| 1840 |
34.1Km |
椎原峠
(765m) |
ここまでは登山客が多いゆえ、整った道をすごいスピードで進む。時速4Kmは下界と変わらぬスピードだった。椎原峠でしばし休憩。疲れがピークに達し、テンションが下がりすぎていたので、ここでリボビタン投入。
|
| 1944 |
36.4Km |
小爪峠
(775m) |
金山が近づいてきた。あたりは何も見えない。リボビタンのおかげでテンションが恢復。自分だけ妙な饒舌になっていた。
|
| 2055 |
39.0Km |
金山分岐
(967m) |
軽い岩場を乗り越えて、金山分岐到着。しばし休憩。入念なストレッチを施す。出発前に金山山頂をピストンで踏む。分岐から意外と近かった。
|
|
|
|
 |
| 2210 |
|
|
アゴ坂峠まで思いっきり下り、しばらく三瀬山(846m)の急な登りに転じ、最後に目一杯下って三瀬峠。途中一度三瀬峠の手前で休憩を挟んだ。意識はハッキリしているが、脚の筋肉が酷く痛い。
|
|
42.9Km |
三瀬峠
(581m) |
車道にクルマがいないときを見計らってさっさと横断する。休憩無しのスルー。雷山まで
9Km弱の看板が。ここから井原山まで 4.2Kmの道のりが酷い。闇の中、脊振山系随一とも言われる
400mの急登を歩かなくてはならない。ここにきて脚が悲鳴を上げている、というかは、骨の髄がズキズキと痛む。痛みに耐えて脂汗が出る。さらに痛みによって吐き気を催してくるという最悪の状態になっていた。二つある新村分岐の真ん中でいったん休憩したが、休憩は別になんてこと無いものの、休憩から再び歩き始めると、叫び声をあげたくなるくらいスネの骨とヒザが痛い。新村・水無分岐から標高差
300mの登り。意識無く、ひたすら脚を運ぶことに徹した。何度も休憩を申し出たい気持ちになったが、それを声にする余裕も無かった。さらにさらに、時折すぐ脇から獣がバサバサという大きな羽音を立てて逃げて行く音が聞こえる。非常に不気味な登山道だ。
|
| 2310 |
47.1Km |
井原山
(983m) |
何度かの偽ピークを踏み越え、井原山頂になだれ込んだ。山頂直前にこんな時間にもかかわらず人の声が聞こえたので、ついに幻聴かとわが耳を疑った。しかしなんと、山頂には人がいた。お互い、姿を確認してひどく驚いた。テントを張って、ビバークするようであるが、どうやら目的は山頂からの夜景見物だった模様。実際、ここの夜景はすごい。福岡都市圏、そして有明海側まですべての夜景をこの目で見て取れる。だが写真に残す体力も気力も無かった。靴下を脱いで足を冷やし、ラストの雷山に備える。 |
| 0145 |
50.5Km |
雷山山頂
(955m) |
1度の休憩を挟み、やっと雷山山頂に到達。初日の目標地点だ。ここで記念撮影をする。すでに体力は消耗しきっていた。遠く、羽金山の電波塔の照明がよく見える。
|
|
|
|
 |
| 0221 |
51.5Km |
雷山避難小屋 |
スキー場跡の急な下りを駆け下り、避難小屋に到着。幸い、小屋は無人だった。ここで 4時間の仮眠を含めた長時間休憩を取る。このとき自分は足の状態を考えると、ここでリタイヤする可能性を相当考えていた。しかしリタイヤするにも翌朝、そして下山するにしてもそこそこの距離を歩く必要があるので、脚の痛みが残ると厳しい。それを鑑みて、小一時間かけて入念なストレッチを施したのち、シュラフへともぐりこんだ。 |
| 630 |
|
|
泥のように眠り込むとはまさにこのことか。 1度もまったく目を覚ますことなく、日の出を迎えた。脚の状態を確かめようと身体を起こすと
…なんと!信じられないことに、痛みがまったく無い。ついに神経が狂ったかとも思ったが、ストレッチ効果だろうか、ともかく全然歩けるのである。これは脊振の女神が私に微笑んだか…ともかく、この瞬間にリタイヤのリの字は完全に消え去り、残り25Km超を気合で消化することに決めた。
|
| 729 |
|
|
水汲みをして、出発。 |
|
|
|
 |
|
|
|
長野峠までは、ここからオニのような下り。しかも、道は荒れ放題でよくわからない。このルートを使う登山客がほぼ皆無だということを考えれば当然か。
|
| 817 |
53.7Km |
長野峠
(542m) |
県道12号線とクロスする、長野峠に到着。小休止。 |
|
|
|
 |
|
|
|
ここから羽金山の登りとなる。先輩から朝一番にキツいと聞かされていたので、怯えながら登る。途中40分歩いて休憩を取るまでは大した登りではなかったが、山腹に取り付いてから最後の
250mの急登に喘がずにはいられなかった。ここでも、山頂の手前まで来たところで急に40mくらい急降下させられ、最後に
50mを登って山頂となる意地の悪いルートであった。九千部、脊振、そしてここ羽金と、山頂に人工物のあるところは、登山道が一般に迂回を強いられる。 |
| 1010 |
57.4Km |
羽金山頂
(900m) |
電波時計の電波送信局である山頂に到着。200mもの高さの電波等が立ち、南は与那国から、東はだいたい箱根までの範囲をカバーしている。(電波自体はなんと択捉島の南端や、万里の長城のあたりまで届いている)ちなみに電波送信局はここ羽金山と、福島県の大鷹鳥谷山の2局のみ。この2局で日本全域の電波をまかなっている。 |
|
|
|
 |
|
|
|
疲れた足を休めて、荒川峠へ向けて出発。羽金山を出るといったん下るも、また羽金山とほとんど変わらない高さまで上がり、そしてやっと本格的なくだりになる。だらだらと下る道だが、通行量が少ないようで、かなり荒れ気味の道。スピードが出なくなるし、つまづくし、体力も気力も削ってゆく。
|
| 1233 |
62.3Km |
荒川峠
(585m) |
近くにサーキット場でもあるのか、なにやらカートのタイヤのような音が聞こえてくると荒川峠である。荒川峠からだらだらとした登りに転じ、植林の森を歩いてゆく。途中で分岐した道の案内板に、「右折深江」とある。もうJRの筑前深江までやってきたのか。しばし進むと、前からなんとオフロードバイクがやってきた。登山道でバイク、
、、、OKなのか?そんなことよりも、よくぞ重たいバイクでここまでやってきたなと思うほど、道が整っていなかった。 |
| 1350 |
64.8Km |
女岳
(748m) |
最後が急坂となりたどり着いた山頂は、糸島半島や姫島が一望できる素晴らしい景観。しばし休憩する。 |
|
|
|
 |
|
|
|
下り始めると、突如先ほどまで元気だった先輩が「膝が痛い」と顔をゆがませて訴え出た。普段苦しい顔を見せたことが無い先輩ゆえ、なにかただならぬ予感がした。疲労骨折だろうか。ペースに気を配り、なんとか荒谷峠まで下る。
|
| 1414 |
65.5Km |
荒谷峠
(542m) |
ドラスティックな下りを終え、細い舗装路とクロスしたところで荒谷峠。本来ならここから浮岳の登りに入るところだが、負傷者が出たため、浮岳山頂は迂回することとして、山腹の林道を行くことに。だが、登山靴での林道歩きは逆に足の裏にまた別の負担をかけることとなる。 |
|
|
|
 |
|
|
|
七山村側の林道を進む。アップダウンはひどくないものの、九十九折れになり先が見えない。途中休憩を取り、新聞紙を丸めたものとテーピングテープで負傷した先輩の膝に添え木を施し、曲がらないように固定した。すると、苦痛が少し和らぎ、歩きやすくなったようだ。 |
|
|
|
しかしこの林道歩きは足に、とくに足首にものすごい負担がかかる。クッション性が無いので、足を打撲させているような感じだ。さらにそれをかばっていると次は腰に来る。林道歩きは長距離するものではない。
|
|
|
|
 |
| 1614 |
71.5Km |
白木峠
(355m) |
長時間の林道歩きを終え、白木峠到着。峠の佐賀県側一帯はゴルフ場となっている。ここで脊振山系最後の山、十坊山に登るグループと、そのまま福吉へ一足早く下るグループとに分かれる。初完走がかかっているT先輩と私が十坊山へ、負傷した先輩と2人のK先輩は既に一度完走しているので、直接福吉へ下ることになった。まず、十坊山組から登山道に入って、出発。 |
|
|
|
 |
|
|
|
体力の有り余る T先輩のペースは速く、息を切らしながらなんとか着いて行く感じだった。一度ニセピークに心折られながらも、白木峠出発からわずか22分で山頂が見えてきた。 |
| 1643 |
72.6Km |
十坊山
(535m) |
原田駅を出発して、長いこと 33時間。やっと唐津湾の眺めが美しい脊振終点の山、十坊山に到達。最後に飛ばしたことですこし足が痛いが、それよりも到達したという感動が大きかった。セルフタイマーで撮影しようとしていると、山頂に居たオバチャンがシャッターを押してくれた。しばし感慨に浸りながら休む。 |
|
|
|
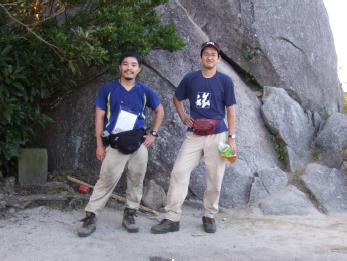 |
|
|
|
こうなれば次は日暮れが襲ってくるので、なんとしても明るいうちに下山したいという気持ちが足を動かす。ものすごいスピードで福吉駅へ向かう登山道を駆け下りる。
|
| 1726 |
75.7Km |
|
登山道出口登山道の終点である、みかん畑に到着。ここから舗装路となる。しかし国土地理院の地図に無い農道が出来ており、しばし迷う。 |
|
|
|
大きく遠回りを繰り返しながら、やっと県道に出た。ここの県道から海側へ出れば、福吉駅。山側に行けばまむし温泉である。私は温泉によりたかったので山側へ、先輩は岐路を急ぐとのコトで海側へとそれぞれ針路をとる。「おつかれさまでした!」
|
| 1805 |
78.0Km |
まむし温泉 |
ゴール。白木峠から県道経由で下山し、先に到着していた 3人の先輩と浴槽で再会。無事完走したことを報告し、汗を流す。風呂上りには伊都物語の牛乳を飲み、締めくくりとした。 |
| ※距離は国土地理院発行2万5千図にて計測したもの。よって、実距離より短く表示されている。実歩行距離はキロ数に×1.2〜1.4程度したものと推測される。 |
|
〜感想〜
体力の限界と言うのは、自分で作るものではなく神が思し召してくれるもの。よって、間違ってもリタイヤなどと言う愚言を自ら口にしてはいけない。歩き、足が動かなくなるまで歩くのだ。歩けなくなっても、歩くのだ。
ただ、一ついえるのは達成感とともに、なぜこのようなバカをしたのかという疑問が、帰りの筑肥線の車内で浮かび上がってきた。一度やれば、もういい。もう通しで歩かなくていい。
しかし、来年も、そして再来年もこのような愚行に走る勇者が現れることを願ってやまない。 |
|